SCROLL DOWN
INFORMATION
生産性を上げる方法は?メリットやおすすめ施策、具体的な事例を紹介

ビジネスの現場では、限られた時間や人員の中で最大限の成果を出すことが求められます。そのために欠かせないのが「生産性を上げる方法」を理解し、実践することです。
生産性が向上すれば、同じリソースでもより多くの成果を出せるだけでなく、残業の削減や従業員満足度の向上にもつながります。また、競争が激しい市場環境においては、効率的な働き方を実現できるかどうかが、企業における成長のチャンスを左右します。
本記事では、生産性を上げるメリットや具体的な施策、事例を交えて分かりやすく解説します。日々の業務改善や組織改革のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
そもそも生産性とは?

「生産性」とは、投入した資源に対してどれだけの成果を上げられたかを示す指標です。資源には、人の労働時間やスキル、設備や資金などが含まれ、成果は売上や利益、サービスの質などが挙げられます。
例えば、同じ時間でより多くの製品を作れる、あるいは少ないコストで高品質なサービスを提供できる場合、生産性が高いといえます。
つまり、単純に作業スピードを上げることだけではなく、効率と成果のバランスを高めることが重要なのです。
「生産性を上げる」とはどういうこと?
「生産性を向上する」とは、同じ時間やコスト、労力といった限られた資源を用いながら、より大きな成果を生み出すことを意味します。作業量を増やすことだけではなく、無駄を減らし効率的に業務を進めることで、質と量の両面でアウトプットを高めることが重要です。
例えば、業務フローを見直して重複作業をなくす、ITツールを導入して入力作業を自動化する、といった取り組みは代表的な例です。無駄な作業を減らしたり、自動化を進めたりすることで社員は付加価値の高い業務に集中でき、企業にとっては利益拡大や競争力強化につながります。これが「生産性を向上させる」ということです。
また、従業員にとっても残業削減や働きやすさの向上といったメリットが生まれるため、生産性向上は企業成長と働き方改革の両立に欠かせない考え方といえるでしょう。
生産性の主な指標
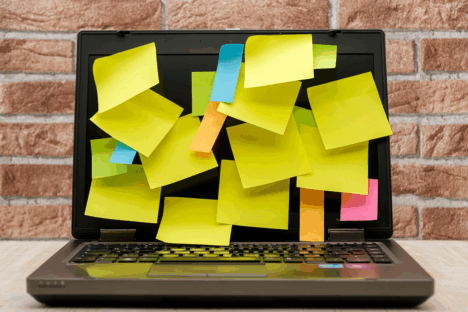
生産性を測る際には、何を「成果」とみなすかによって指標が異なります。代表的なのが「付加価値労働生産性」と「物的労働生産性」です。
ここからは、生産性のそれぞれの指標について解説します。
付加価値労働生産性
付加価値労働生産性とは、企業や組織が生み出した付加価値を従業員一人あたり、または労働時間あたりで割って算出する指標です。
付加価値とは、売上高から原材料費や外注費などを差し引いた額を指し、企業が実際に新たに生み出した価値を示します。この数値が高いほど、従業員が効率よく価値を創出していると判断できます。
特にサービス業や小売業のように製品数量で成果を測りにくい業種では、経営改善の有効な指標となります。また、この指標を高めるには単にコスト削減だけでなく、新商品開発やブランド価値向上など「収益を伸ばす施策」も重要です。
つまり、付加価値労働生産性は企業の収益力や競争力を総合的に示すものといえます。
物的労働生産性
物的労働生産性とは、生産量を労働投入量で割って算出する指標であり、特に製造業や農業などモノづくりの現場でよく使われます。
例えば、1時間あたりに何個の製品を作れるか、1人の従業員が1日にどれだけの生産量を生み出せるかといった形で測定が可能です。この数値が高いほど、同じ労働力で多くの成果を出せていることを意味します。
物的労働生産性の改善のためには、生産ラインの効率化や設備投資、技能教育などが効果的です。ただし、単純に数量を追求するだけでは品質が犠牲になるリスクもあるため、効率と品質のバランスを調整する必要があります。
物的労働生産性は、現場の生産効率を把握しながら、改善を進めるうえで重要な基準となるのです。
生産性を上げるメリット

生産性を上げることは、業務効率化にとどまらず、さまざまな領域でメリットがあります。ここからは、生産性を上げるメリットを解説します。
各種コストを削減できる
生産性向上の主なメリットとして、まず挙げられるのがコスト削減です。例えば、ITツールを活用して事務作業を自動化すれば、人手による入力や確認作業の時間を大幅に削減できます。
製造業であれば、生産ラインを標準化し、工程を見直すことで材料ロスや在庫コストを抑えられます。物流業では配送ルートを見直すことで燃料費の削減や稼働効率の改善につながる可能性があるでしょう。
また、会議の効率化やリモートワークの活用で、会場費や交通費といった間接コストも見直せます。いずれも、単純な経費削減としてだけではなく、従業員がより付加価値の高い業務に時間を割けるのがメリットです。
人材不足を解消できる
慢性的な人材不足は多くの業界で課題となっていますが、生産性向上はこれを補うための施策として検討されることも多いです。業務フローを徹底的に見直し、無駄な作業を削減することで、少ない人員でも同等以上の成果を出せるからです。
実際、問い合わせ対応をチャットボットで自動化すれば、従業員は別の業務に集中できます。製造現場であれば、ロボットやAIを活用して単純作業を任せることで、人材不足を補いつつ、品質を均一に保ちやすくなるといったメリットが得られるでしょう。
さらに、効率的な働き方が実現すれば従業員の満足度が上がり、離職率の低下も実現できる可能性があります。結果的に、新規採用の負担も軽減できるでしょう。
利益率を向上できる
生産性の向上は、売上を大きく伸ばさなくても利益率を改善できるのが魅力です。例えば、同じコストで従来より多くの製品を生産できれば、固定費の比率が低下し、利益率は自然と高まります。
業務効率化によって生まれた時間を新商品の開発やサービス改善に投じれば、付加価値が高まり単価アップにもつながるでしょう。
とくに、品質が安定することは利益率において重要です。製品・サービスの顧客満足度が上がれば、リピーターや口コミによる新規顧客が増加し、広告費を増やさずとも売上を向上できるからです。
人件費や原材料費が高騰する時代において、利益率を高める取り組みは企業の存続に関わる問題であるため、生産性の向上を視野に入れた施策が必要といえます。
競争力を強化できる
競争が激しい市場において、生産性の高さは企業の差別化ポイントとなります。効率的な企業は、低コストで品質の高い商品を提供できるため、価格競争でも優位に立てることが理由です。
また、生産性を向上できれば、あまったリソースを新規事業や研究開発に充てられるため、新たな商品・サービスを生み出しやすくなります。
仮に製造業であれば、効率化で空いたリソースを活かし、短期間で新製品を展開できれば、顧客のニーズにスピーディーに対応でき、競合を引き離すことも可能です。
長期にわたって、市場で優位な立場に立ち続けるためにも、生産性の向上は欠かせない対策であるといえるでしょう。
効率化で空いた時間を新しい施策や研究開発に回せる
生産性が向上すると、従業員一人ひとりの業務に余裕が生まれます。その分、新たな施策や研究開発に時間を投資できれば、企業の成長に影響すると考えられます。
例えば、営業部門で業務自動化を進めれば、社員は顧客との関係を強化したり、新規市場開拓に注力したりできるでしょう。
製造業においても、生産効率化で浮いた時間を使い、品質向上の研究や新技術の導入検討に取り組むことが可能です。効率化で得られた時間を社員教育に充てれば、一人ひとりのスキルアップも促進できます。
つまり、生産性の向上のための取り組みは、企業が未来に向けた投資でもあるのです。
品質の安定化につながる
生産性向上は、効率を上げるだけでなく品質の安定化にも直結します。作業手順を標準化したり、業務プロセスを明確にしたりすることで、担当者のスキルや経験に左右されにくい仕組みを作ることが可能です。
製品やサービスの品質にばらつきが減り、一定の品質を維持して顧客に提供できるようになります。また、効率化で生じる時間の余裕を品質チェックや改善活動に充てれば、さらに品質の安定につなげることが可能です。
仮に飲食業であれば、オペレーションを標準化することで、店舗や時間帯による味や接客の差を最小限に抑えやすくなるでしょう。品質が安定すれば顧客満足度が高まり、リピート率の向上につながるため、生産性の向上は大きなメリットになるといえます。
生産性を上げる方法は?おすすめ施策を解説
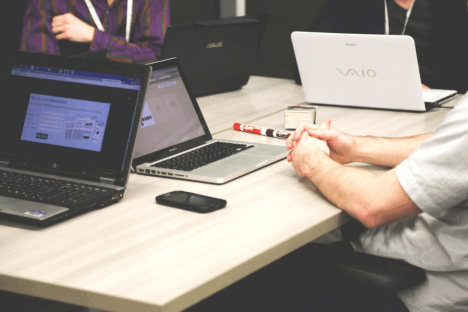
生産性を高めるためには「効率化」と「付加価値向上」の2つのポイントをおさえて施策を考える必要があります。業務のスピードを上げるだけではなく、無駄を削減しながら、従業員がより価値の高い業務に集中できるようにするためにはどうしたらいいのか、以下から見ていきましょう。
通勤時間を短縮する
長時間の通勤は従業員にとって大きな負担です。疲労やストレスで仕事の集中力やモチベーションを低下させる恐れもあります。生産性を高めるには、この通勤時間を短縮する工夫が効果的です。
リモートワークやテレワーク制度を導入すれば、従業員は移動時間を削減し、その分を仕事や自己研鑽に充てられるでしょう。
企業によっては交通費削減にもつながり、コスト面のメリットも得られます。通勤時間の短縮は、従業員のワークライフバランス改善にも直結するため、離職率の低下や採用力の向上にも良い影響を与えるものです。
生産性向上を従業員の健康や生活満足度を高める投資として捉えると、組織全体の生産性を底上げする施策として成功しやすいでしょう。
関連記事:サテライトオフィスは意味ない?効果的な活用法と成功するためのポイントを徹底解説
ワークライフバランスを改善する
ワークライフバランスの改善は、生産性向上における重要な部分です。従業員が心身ともに健康であることが、集中力を高め、結果的に業務効率の改善につながります。
そのため、過度な残業を抑える仕組みづくりや、有給休暇の取得を推進する制度がおすすめです。また、柔軟な勤務形態を導入し、子育てや介護と仕事を両立できる環境を整えることも検討しましょう。
従業員が「安心して働ける」と感じる環境はモチベーションを高め、定着率やパフォーマンス向上につなげます。結果的に人材の流出を防ぐことにもつながるため、人手不足に悩む現場にもメリットがあります。
集中できる環境を確保する
生産性を上げるためにも必要なのが、従業員が集中して業務に取り組める環境です。オフィスでは、騒音や不要なコミュニケーションが集中を妨げることがあります。
パーテーションや防音対策を導入したり、フリーアドレス制で自分に合う環境で作業できるようにしたりするなどの工夫が有効です。
また、無駄な会議やメールを減らし、業務に集中できる時間を確保することも重要です。会議は「本当に必要か」「誰が参加すべきか」などを明確にしたうえで実施し、メールではむやみに「CC」に関係者を入れすぎないようにしましょう。
「必要か」を基準として業務を整備することで、従業員が集中できる環境を確保しやすくなります。
チームワークを強化する
生産性を上げるためにも、個人の能力を最大限発揮するだけでなく、チームとして力を合わせることを意識しましょう。社内での情報共有が滞ると業務の重複やミスが発生し、非効率な事態に陥ってしまいます。
定期的にミーティングを実施したり、チャットツールを活用したりして、情報共有をルール化することがおすすめです。
また、役割分担を明確化し、各メンバーが自分の作業範囲を理解できるようにしておきましょう。複数人が同じ作業をしてしまう…といった無駄を防ぎやすくなります。
採用力を向上する
生産性を高めるにあたり、欠かせないのが優秀な人材の確保です。採用力を高めることで、新しいアイデアやスキルを持つ人材を獲得できます。
本記事でも触れた通り、求人票には給与や福利厚生だけでなく、キャリアパスや働きがいを記載することが大切です。
また、リモート勤務やフレックス制度といった柔軟な働き方も導入し、多様な人材を獲得できるように社内体制を整備していきましょう。
ITツールを導入する
ITツールの導入は、生産性を高めるための方法として代表的な施策です。勤怠管理や経費精算をシステム化すれば、従業員は事務作業に時間を取られず、本来の業務に集中できます。
チャットツールやプロジェクト管理ツールを使えば、情報共有も円滑になり、意思決定までのスピードも上がります。場所や時間を問わず情報を確認できるため、各々が自分の都合に合わせやすいのも魅力です。
さらに、AIを活用したデータ分析や予測ツールを導入することで、成功率の高い戦略立案につなげることも可能です。近年は、新しい技術を反映したツールが多数展開されているため、企業の業種や風土、規模などにマッチするツールを探してみましょう。
社内の体制を見直し・改善する
生産性の向上が期待できる施策をどれだけ導入しても、社内の体制が非効率であれば十分な効果は期待できません。
生産性向上を進めるためには、組織体制そのものを見直す必要があります。例えば、意思決定のスピードに課題があるなら、さまざまな権限を現場に与えて意思決定の時間を短縮することが有効です。
また、社内の情報共有のあり方に問題があるなら、部署間の縦割りをなくして横断的に連携できる体制を構築する、といった改善がおすすめです。各部署が連携できるようになると、各部署が持つ情報を全部署で共有しやすくなり、無駄の洗い出しやさらなる効率化のヒントにつながります。
実際に生産性向上を実現した企業の事例

生産性を高めることが重要とはいえ、具体的にどのような取り組みを実施すればいいのか、実際に効果を得られた企業はどのような恩恵があったのか、など気になる部分は多いのではないでしょうか。
ここからは、生産性向上に成功した企業の主な事例についてご紹介します。
サテライトオフィスを活用したケース
あるIT企業では、地方にサテライトオフィスを開設し、従業員が自宅から近い拠点を選んで勤務できるようにしました。これにより片道1〜2時間かかっていた通勤が30分以内に短縮され、従業員の疲労軽減やワークライフバランス改善が実現できたのです。
浮いた時間を自己研鑽や新規プロジェクトに充てることが可能になり、結果として業務効率が向上しました。さらに、地域に根差した採用もしやすくなり、優秀な人材確保にもつながりました。
企業にとっては交通費やオフィス維持費の削減効果もあり、従業員と会社双方にメリットをもたらす施策となったといえます。
上記をふまえると、サテライトオフィスは地方創生やテレワーク普及とも相性が良く、今後ますます活用が広がると考えられるでしょう。
関連記事:サテライトオフィスと支店の違いとは?それぞれの特徴と選び方を解説
クラウド管理システムを導入したケース
製造業を営む中小企業では、従来エクセルや紙で行っていた在庫・受注・工程管理をクラウド型の管理システムに移行しました。結果的に、各部門がリアルタイムで最新情報を共有できるようになり、在庫過多や発注遅延といったトラブルが大幅に減少しました。
特に、経営層はクラウド上でデータをスピーディーに把握できるため、経営判断のスピードが飛躍的に向上したのです。在宅勤務や外出先からでもシステムにアクセスできるため、コロナ禍でも事業を止めることなく継続できた点も大きな成果でしょう。
上記の取り組みにより、管理コストは20%削減され、納期遵守率は95%以上に改善しました。クラウド管理システムは効率化だけではなく、企業の対応力を高めることにもつながったのです。
労働環境を改善したケース
サービス業として展開しているある企業では、慢性的な長時間労働と離職率の高さが課題となっていました。そこで取り組んだのが労働環境の改善です。
まず、シフト管理を見直し、無理のない勤務体制を整備しました。そのうえで、残業を削減するために業務プロセスを標準化し、作業マニュアルを整えました。
休憩室やリフレッシュスペースを設けるなど職場環境の整備にも投資したことで、従業員満足度が上がり、離職率は従来の半分にまで低下させることに成功したのです。
定着率が向上したことで教育コストも削減され、顧客対応の品質が安定化しました。さらに、従業員が健康的に働けるようになったことで売上増加も実現しています。
労働環境の改善が「人材の定着」「サービス品質」「収益力」の三つを同時に押し上げる成功事例となったのです。
生産性を高めるならサテライトオフィスの導入がおすすめ

生産性を上げる方法として、ぜひ検討したいのがサテライトオフィスの導入です。
ここからは、とくにおすすめの「富士宮市の事業」についてご紹介します。
富士宮市ではサテライトオフィス推進事業を展開
富士宮市では、「富士宮サテライトオフィス」として、サテライトオフィス設置の支援を行っています。もともと、富士宮市は資源が豊富でビジネスに最適な街として知られているのが特徴です。
飲食関連やサービス業、製造業など、業種を問わずさまざまな企業が進出している街でもあります。
そんな富士宮市に拠点を設けたいといった声も多く、手軽に導入できる選択肢としてサテライトオフィスの推進事業を展開しているのです。
無料で相談できるため、まずは一度以下の窓口にて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
【富士宮サテライトオフィス】
窓口 :富士宮市 産業振興部 商工振興課
電話番号:0544-22-1154
公式HP :https://fujinomiya-so.com/
関連記事:起業なら富士宮市がベスト!創業場所として選ぶメリットや補助金、支援内容を解説
コワーキングスペースなら小規模オフィスを低コストで導入可能
富士宮市では、サテライトオフィスだけではなく「Connected Studio i/HUB」というコワーキングスペースも運営されています。カフェ感覚で気軽に立ち寄りやすいのが特徴で、一日単位や時間単位での利用も可能です。
「リモートワークを導入しているものの従業員が集中できていない」といった課題を抱えている企業にとって、コワーキングスペースは便利な存在でしょう。
また、Connected Studio i/HUBは、インターネット環境や電源はもちろんのこと、会議室やテレフォンブースなど、業務に必要な設備も整っています。
富士宮市で気軽に利用できる作業スペースが欲しいと考えている方は、ぜひコワーキングスペースの利用を検討してみてください。

【Connected Studio i/HUB】
住所 :静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル1F/2F
営業時間:9:00~18:00(月額会員は24時間利用可能)
休業日 :土曜日・日曜日・祝日・その他
電話番号:0544-66-6880
公式HP :https://connectedstudioihub.com/access/
まとめ
生産性を高めることは、企業にとって単なる業務効率化以上の意味があります。コスト削減や利益率の改善といった直接的な成果だけでなく、従業員のワークライフバランス改善や人材不足解消、品質の安定化など、多方面にメリットがあるのです。
生産性を高める取り組みを導入したり、環境を整備したりすることは決して簡単なことではありません。ただ、きちんと整備できれば長期的にメリットを得られるのは事実です。
社内の業務や人員、風土、環境を振り返ってみたときに、「無駄がある」「効率化の余地がある」と感じる場合には、ぜひ本記事を参考にしながら自社に最適な取り組みを計画してみてはいかがでしょうか。
お申込み・お問い合わせはこちら
読まれている記事

