SCROLL DOWN
INFORMATION
オフィス回帰(出社回帰)とは?広がりつつある背景や、検討できる他の選択肢を解説

コロナ禍を経て働き方の再設計が進む中、「オフィス回帰(出社回帰)」が注目されています。生産性を向上したり、企業文化の醸成したりするなど、さまざまなメリットがあるとして、出社を見直す動きがさまざまな企業で見られるようになりました。
一方で、完全出社への切り替えが最適とは限りません。業務特性や人材獲得競争、従業員の通勤負担、オフィスコストを踏まえると、オフィス回帰よりも別の勤務スタイルのほうが適している場合もあります。
そこで、この記事では、オフィス回帰が広がる背景や、オフィス回帰のメリット・デメリットなどについて解説します。
オフィス回帰とは

「オフィス回帰」とは、コロナ禍で普及した在宅勤務やリモートワークから、出社頻度を高めたり常態化させたりする動きを指します。オフィス回帰と聞くと、完全出社へ切り替えるイメージがありますが、実際には、週数日の出社を前提としたハイブリッド型や、特定業務のみ出社する選択的な運用も該当します。
オフィス回帰における主な目的は、生産性やコミュニケーション、企業文化の維持、教育や評価のしやすさ、情報管理など多岐にわたります。オフィスに出社して従業員が集まる価値を改めて定義し、対面だからこそ得られる学びや意思決定のスピードを取り戻すことを狙いとしています。
とはいえ、オフィス回帰は一律の「出社義務化」を意味するわけではありません。職種や業務の特性、通勤負担などの条件に応じて、最適な勤務スタイルを選ぶ必要があります。
オフィス回帰が注目される理由

一度はリモートワークが中心となったものの、改めてオフィスへの出社スタイルが注目されるのはなぜなのでしょうか。
ここからは、オフィス回帰が注目される理由について解説します。
生産性への懸念がある
オフィス回帰が注目される理由として、まず挙げられるのが生産性への懸念があることです。在宅中心の勤務では、連絡の行き違いや情報の分断が生じやすいといったデメリットがあります。結果的に、判断の速さに影響したり、再現性が低下したりするかもしれません。
実際、やり取りがチャットやメールなどの「メッセージ」がメインになると、前提の共有が薄れてしまい、確認の往復が増えてしまうことがあります。さらに、着手に遅れが生じたり、認識の齟齬によってミスにつながったりする可能性も考えられます。
とくに入社して間もない従業員や異動してきて日が浅い従業員は周囲の何気ない会話から学ぶ機会が少なくなりやすいものです。結果的に、教育コストが膨らみやすくなります。
ただ、「集中が必要な作業」はリモートのほうが進むケースもあります。実際「自宅なら他の従業員に話しかけられないから進みやすい」「自分のタイミングでチャットでコミュニケーションを取れるから集中時間を確保しやすい」と感じる方は少なくありません。
つまり、オフィス回帰が必ず生産性につながるのか、今一度見直したうえで判断する必要があるのです。
企業文化が影響している
オフィス回帰が注目される背景には、企業文化が影響しているケースもあります。企業文化は、制度やスローガンだけでは育ちません。挨拶や雑談、判断の基準合わせといった日々のやり取りで構築されていきます。
完全なリモートでは、企業特有の価値観を共有したり、先輩の振る舞いを見たりする機会が減り、企業文化が伝わりにくくなることがあります。とりわけ、顧客志向や品質基準、リーダーの期待行動は、対面の体験を通じて理解することが多いです。
オフィス回帰は、こうした「文化を体感する場」を計画的に増やす試みでもあります。ただし、単なる出社の義務付けは従業員から反発を招く恐れもあるのが事実です。文化について言葉にし、どのようなシーンが「対面で対応することが望ましい」とされるのかを明確にし、従業員が納得できるように準備しておく必要があります。
共同での作業における質低下に懸念がある

オフィス回帰が注目される理由の一つが、共同作業における「質」への影響です。創造性が求められる議論や仕様における決定・詰めなどは、必ずしも事実ベースだけで進められるものではありません。
相手の表情や間合い、その場のひらめきに任せて描いたラフな図解なども手掛かりになるものです。対面であればこうした手がかりは得やすい傾向にあり、共同作業における大きなメリットでもあります。
しかし、完全リモートの場合、オンラインでのやりとりとなります。お互いの発言が重ならないよう遠慮しあってしまい、アイデアの発言が減少したり、情報をまとめたりするテンポが遅れがちです。
また、議論を進めていくにあたって、感じた細かな違和感を共有することも難しくなり、ブラッシュアップにおいても問題が生じてしまうかもしれません。当然、議論しながら、その場で試行錯誤していくことも難しくなるでしょう。
柔軟な発想が求められる場面では、オフィス回帰が最適なケースがあると考えられます。
オフィス回帰のメリット

オフィス回帰を検討するにあたって、気になるのがメリットではないでしょうか。
仮に、オフィスへの出社スタイルに切り替えた場合、どのようなメリットが得られるのかを解説していきます。
生産性を向上できる
オフィス回帰における大きなメリットであるのが、生産性を向上できる点です。対面では前提の共有が速く、意思決定に必要な情報が短時間で集まります。
ホワイトボードや紙の資料を併用しながら議論を進められるため、情報整理から意思決定までもスピーディーです。
また、新入社員や異動して間もない社員としては、上記のような周囲の仕事ぶりから学びを得やすく、教育期間を短縮することにもつながります。結果的に教育におけるコストを削減することも期待できるでしょう。
他にも「自宅では監視されていないから集中できない」「オンオフの切り替えができず仕事がはかどらない」といった従業員にとってもオフィス回帰はメリットです。出社することで仕事モードに切り替えやすく、業務に打ち込みやすくなるといった声もあります。
従業員の声に耳を傾けながら、オフィス回帰のタイミングや、出社頻度などを検討していくといいでしょう。
コミュニケーションの質・量を向上できる

オフィス回帰によって、コミュニケーションの面でメリットを得られます。出社スタイルに切り替えることで、オンライン会議だけでは拾いきれない表情や間の取り方などを、対面では自然に受け取れます。
自分の発言に対する反応が分かれば、双方の誤解を軽減できるでしょう。そのうえ、出社していれば、オフィスで声をかけるハードルも低くなり、コミュニケーション不足や情報共有不足なども減らせる可能性が高まります。
また、他部署との定例やランチ交流などの機会を設けることで、部門間の壁も崩しやすくなるでしょう。部署間の情報共有や連携を深めることができ、新たな成長機会を得たり、ビジネスチャンスを見つけたりすることも考えられます。
帰属意識や結束感を向上できる
オフィス回帰に切り替えることで、帰属意識やメンバーとの結束感を向上できるといったメリットがあります。同じ環境で働くことは、企業の理念や価値観を体でつかむ感覚につながるからです。
日々の挨拶や雑談、声かけ、ちょっとした助け合いが積み重なり、仲間意識が育ちます。管理職の「手本となる行動」を他の従業員が目にしやすく、どのような振る舞いが企業から期待されるのかを伝えられるといったメリットもあるでしょう。
結果的に、従業員の意識の変化や、モチベーションの向上、育成につなげることができ、企業を支える人材を増やしやすくなります。
育成・マネジメントがしやすい
育成やマネジメントがしやすくなる点は、オフィス回帰におけるメリットの一つです。従業員が出社することで、対面でコミュニケーション機会が増え、メンバーの疑問や迷いに気づきやすくなるからです。
上司や先輩、管理職などが、手本を示しながら、新入社員や転職・異動間もない従業員のスキルを引き上げることができます。実際、オンラインでやりとりするよりも、対面の1on1のほうが場の空気や感情の変化を拾いやすく、声をかけるタイミングを逃しにくくなります。
また、評価の面では一人ひとりの成果だけでなく、成果を得るまでの過程も把握しやすいのが魅力です。評価される側の従業員としても、納得できる評価を得やすいといえます。
オン・オフを切り替えやすい
オフィス回帰における大きなメリットであるのが、従業員がオンとオフを切り替えやすくなることです。リモートワークの場合、家と仕事の場所が重なると境界が曖昧になりやすいものです。
自宅にいてもリラックスしにくく、休息の質が落ちることがあります。また、自宅での作業では「リラックスモードから抜けられない」と、業務の質の低下を招くことも考えられるでしょう。
オフィス回帰に切り替えれば、出社が「オン」の合図になり、仕事モードに入りやすくなります。リモートワークにありがちな「少し休みたい」「家事を済ませたい」といった誘惑もなくなり、目の前の業務に集中しやすくなるでしょう。
そのうえ、終業後は職場を離れることが「オフ」への切り替えにつながります。必然的に、自宅が休息の場となるため、生活のリズムも整えやすくなるのです。
オフィス回帰のデメリット
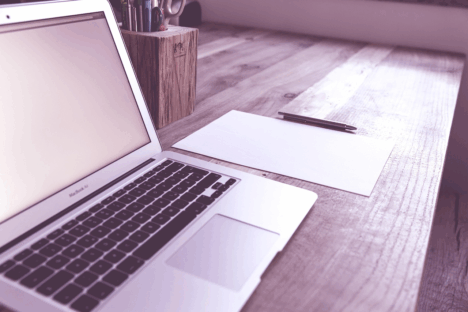
オフィス回帰には、魅力的なメリットがある一方でデメリットも存在します。
具体的に、どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。
ワークライフバランスに影響するリスクがある
オフィス回帰におけるデメリットとして、まず挙げられるのがワークライフバランスに関する影響です。出社が増えると、通勤の往復や始業・終業時間の固定により、従業員が一日に使える自由な時間が減りやすくなります。
とくに、家事や育児、介護と両立している従業員の場合、時間調整が難しくなるケースも増え、疲れがたまりやすくなります。場合によっては、体調不良に伴う欠勤や休業、離職などにつながるかもしれません。
また、オフィスでの会議や雑談が長引くと、自宅よりも集中時間を確保しにくくなります。実際、「オフィス回帰に切り替えたら従業員の生産性が下がった」といった声も少なくありません。
集中作業が多い業種・職種の場合は、とくに上記の影響を受けやすいと考えられます。
従業員の満足度低下の懸念がある
オフィス回帰において、注意したいのが従業員の満足度の低下です。リモートワークのような、自由度の高い働き方に慣れた従業員にとって、出社は抵抗を感じる場合があります。
通勤の負担や外食による昼食費の増加はとくに不満が挙がりやすい部分です。また、リモートワークの導入に伴い、自宅の仕事環境を整えた従業員としても、「わざわざお金と時間をかけて環境を整えたのに」と不満を感じることになるでしょう。
オフィス回帰を検討するのであれば、従業員が納得できる「妥当性」「必要性」をきちんと共有する必要があると考えられます。
出社社員とリモート社員で評価に差が生じやすい
オフィス回帰に伴い、出社もリモートも選べる環境にする場合、働き方の違いで評価に差が生じやすいといったデメリットがあります。顔を合わせる機会が多い「出社社員」のほうが評価が挙がりやすく、在宅中心の従業員の評価が下がりやすい傾向にあるのです。
原因としては、リモート社員の場合は、成果のみが評価基準になりやすく、「成果を得るまでの過程」「普段の勤務態度」などが見えにくくなるからです。
リモート社員の不満につながる恐れがあるため、どのような基準で評価を進めるべきかを改めて見直す必要があるでしょう。
情報共有・報連相を口頭で済ませやすくなりミスにつながる恐れがある

オフィス回帰の意外なデメリットであるのが、情報共有や報連相などに伴うミスが増えるリスクです。リモートワークの場合、メールやチャットなど、記録として情報共有・報連相の内容を残しやすいといったメリットがあります。
後から送受信の内容を見直すことも可能であり、「忘れにくい」「言った言わないを防ぎやすい」などの特徴があります。
一方、出社すると口頭で情報共有や報連相を行うケースが増えることが多いです。「指示されていたのに忘れた」「言われた覚えがないが、相手は伝えたと言い張っている」といったトラブルに陥ってしまうかもしれません。
結果的に、手戻りが発生したり、業務における質の低下を招きやすくなります。オフィス回帰を検討するのであれば、情報共有や報連相のあり方について考え、トラブルを軽減できるようなルール整備が必要でしょう。
固定費が増大する恐れがある
オフィス回帰における大きなデメリットが、コスト面の問題です。従業員の出社比率が上がると、必然的にオフィス面積や座席数、設備投資、清掃、光熱費が増えやすくなります。
さらに、従業員に対する通勤補助や福利厚生、来客対応の費用も積み上がり、総コストが膨らみやすくなるでしょう。コスト削減に力を入れている企業としては、固定費の増大は大きな問題なのではないでしょうか。
出社日に重要度の高い業務や、企業において価値の高い作業を集約し、不要な滞在を抑えるなど、時間あたりの効率を高めるような工夫が求められます。
オフィス回帰を進める際のポイント

オフィス回帰を進めるのであれば、あらかじめ把握しておくべきポイントがあります。
具体的に、どのようなポイントがあるのか、以下を確認しておきましょう。
「なぜオフィス回帰するのか」の目的を明確にする
オフィス回帰を進めるにあたり、まずポイントとなるのが「目的を明確にすること」です。目的が曖昧なオフィス回帰は、従業員の通勤負担のみが増えてしまいます。
そのため、「何を改善したいのか」といった基準でオフィス回帰を目指していき、以下の項目をどう測るのかを明確にしましょう。
- 意思決定のスピード
- 立ち上がり期間
- 商談の創出
- 品質不良の低減
漠然と「出社メインにする」と決定するのではなく、何のためのオフィス回帰なのか、オフィス回帰に切り替えて何が得られるのか、などを想定することが重要です。
リモート社員が不利にならないようなルール整備
オフィス回帰を進めるにあたって、忘れてはならないのが、出社社員とリモート社員が公平に働けるようなルール整備です。出社とリモートで評価が変わってしまったり、得られる情報の差を防いだりするためのルール整備は必須でしょう。
具体的には、リモート社員や出社社員と問わず、「結果重視の評価」に切り替えたり、「特定のシステムへ記録する習慣」を義務付けたりすることが挙げられます。決定事項は文書に集約し、口頭だけで進めないルールを設けるなど、リモート社員にも配慮した仕組みが望ましいでしょう。
また、1on1や面談の頻度は出社・リモートに関わらず均等にし、昇格の条件や役割の定義を決めます。会議は、出社社員とリモート社員が参加する「ハイブリッド前提」で機材と進行方法を整備し、発言の順番やチャットへの応答方法も工夫しましょう。
スモールスタートを意識する
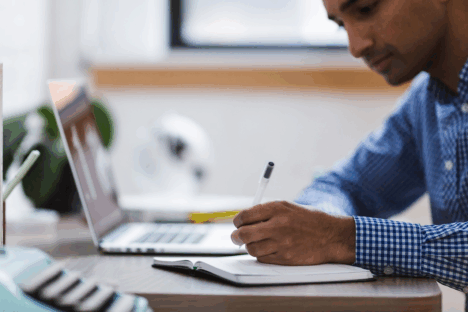
オフィス回帰は、最初から全社で常態化しようとすると、従業員から反発があったり、混乱を招いたりする恐れがあります。そのため、まずは対象部門や曜日を限定するなどして、小規模で始めることが重要です。
意思決定の速度や手戻り率、オンボーディング期間、満足度などのKPIを計測し、オフィス回帰への切り替えが妥当であるかを確認しましょう。
オフィス回帰の運用については、四半期ごとに見直し、席数や会議室、設備への投資と、実際の効果のバランスをチェックしてください。
オフィス回帰のメリットが大きいと判断できるようであれば、徐々に出社率を増やしていくように進めていくことが望ましいでしょう。
あらかじめ従業員の声を集めて運用に反映させる
オフィス回帰は、経営陣のみの判断でスタートするのではなく、従業員の意見も取り入れていく必要があります。
制度の設計段階から、職務の内容や勤務時間、家庭環境など、さまざまな属性の声を拾い、調査や少人数の座談会で課題と期待を見える化しましょう。
とくに、通勤や育児介護、居住地、職種ごとの違いを把握することは重要です。従業員のニーズを把握しないままオフィス回帰に切り替えてしまうと、結果的にリモートワークメインであった時期よりも、生産性が下がったり、離職を招いたりする恐れがあります。
集めた従業員の意見は「必須」「改善」「実験」などに分け、計画内容と責任者を明確にしましょう。定期的に効果や変化を確認し、見える形で全従業員に共有できるようにしてください。
オフィス回帰に伴う「完全出社」以外に検討できる選択肢
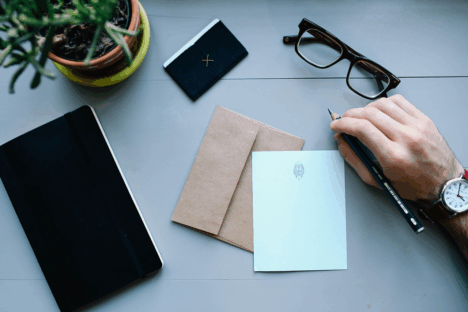
最適な働き方は、必ずしも完全出社とは限りません。他にも、さまざまな選択肢があります。
ここからは、オフィス回帰に伴う完全出社以外に検討できる選択肢として、以下の4つを解説します。
サテライトオフィス
サテライトオフィスとは、本社とは別の小規模拠点のことです。支店・支社とは異なり、あくまでも従業員が出社するためのスペースといったイメージです。
従業員の自宅から近いエリアにサテライトオフィスを設けることで、長時間通勤を避けられるため、疲れや遅刻のリスクを軽減できます。地方にもサテライトオフィスを設けることで、都市部から離れたエリアの従業員の出社負担を軽減したり、新たな人材の雇用チャンスを得たりすることが可能です。
ちなみに、サテライトオフィスは、単純な作業スペースとしてだけではなく、対面での1on1や顧客との面談の場としても活用することができます。
サテライトオフィスを導入する際には利用目的を明確にし、席の予約や入退室の管理、セキュリティの基準を明確にしておきましょう。
ちなみに、富士宮市では、サテライトオフィスの導入を検討している企業向けに、相談窓口を設けています。各種制度や、希望エリアなど、さまざまな相談・案内を行っているため、ぜひ一度お問い合わせください。
【富士宮サテライトオフィス】
窓口 :富士宮市 産業振興部 商工振興課
電話番号:0544-22-1154
公式HP :https://fujinomiya-so.com/
コワーキングスペース
コワーキングスペースとは、自社の拠点として設けるスペースではなく、外部のスペースを借りるようなイメージで利用できる場所です。
コワーキングスペースによって、使用ルールには違いがあるものの「時間単位での利用」「月額での利用」など、さまざまなスタイルでの利用が可能です。つまり、必要なときに必要な席数だけ利用できます。
また、設備が豊富なコワーキングスペースであれば、会議室やテレフォンブース、インターネット環境なども整備されていて、固定費を抑えながら、本来のオフィスのように活用できます。
ただし、不特定多数の利用者が集まる場所でもあるため、利用先を選ぶ際には、機密性やセキュリティ対策の有無、回線品質などについて確認しておくことが重要です。
ちなみに、富士宮市に位置する「Connected Studio i/HUB」は、会議室や通信環境が充実しているコワーキングスペースです。さらに、地元企業や起業家などとの交流機会があり、新しいビジネスチャンスにつながる可能性もあります。
1時間からの利用も可能であるため、気軽に利用できる点もメリットです。

【Connected Studio i/HUB】
住所 :静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル1F/2F
営業時間:9:00~18:00(月額会員は24時間利用可能)
休業日 :土曜日・日曜日・祝日・その他
電話番号:0544-66-6880
公式HP :https://connectedstudioihub.com/access/
フルフレックス制度

フルフレックス制度とは、従来の働き方であるコアタイムを廃止し、開始・終了時刻を個人が自由に決められる制度です。生活リズムや業務の内容などに合わせて働けるため、集中時間を確保しやすく、通院や育児・介護と両立しやすくなります。
また、フルフレックス制度にすることで、通勤ラッシュを避けて出社したり、台風などの災害リスクは高い日には自宅で業務を進めたりするなど、無理のない勤務が実現できるでしょう。
従業員の出勤管理や成果確認など、導入時に定めるべきルールは多いものの、時間の自由度を高められれば、従業員の利便性と生産性を両立しやすくなります。
ハイブリッド勤務スタイル
ハイブリッド勤務スタイルは、業務内容に応じて出社と在宅を組み合わせた働き方です。対面とリモートの強みを活かした勤務スタイルを指します。
意思決定や創造性が必要なミーティング、オンボーディングなどは対面を基本とし、分析やルーチンワークなどは在宅で集中するといった働き方が一般的です。
ハイブリッド勤務スタイルを成功させるためには、出社日と通勤日を従業員が共有できるようにしたり、会議は常にオンラインを併用したりするなど、さまざまな工夫が必要です。とくに、会議やミーティングの場合、議事録や意思決定ログをどう活用・運用するかが重視されます。
とはいえ、何より大切なのは従業員が自分の都合に合わせて出勤とリモートを選べるように環境を整えることです。周囲の同調圧力で「不本意で出社を選ぶ」「本当は出社したいけれどリモートメインの雰囲気だから出社しにくい」といった事態は避けられるようにしましょう。
まとめ
今回はオフィス回帰について解説しました。コロナ禍に伴い、一度はリモート中心のスタイルに変化した企業も、徐々にオフィス回帰に方針を切り替え始めている傾向が見られます。
メリットがあるオフィス回帰ですが、一方でデメリットもあるため、働き方の切り替えを検討する際には、従業員のニーズもふまえて判断する必要があります。とくに、リモートワークがすでに浸透している企業や、リモートワークに切り替えてすでにある程度の期間が経過している場合は、オフィス回帰の切り替えは慎重に判断しなければなりません。
なお、サテライトオフィスを検討中の方は、ぜひ富士宮市にご相談ください。専用の窓口が拠点や補助金などの相談に応じています。
「本社とは別の拠点が欲しい」「リスクに備えてオフィスを分散させたい」「従業員の満足度を向上しつつオフィス出社を促したい」と考えている方は、ぜひ一度富士宮市までお問い合わせください。
お申込み・お問い合わせはこちら
よく読まれてる記事

