SCROLL DOWN
INFORMATION
オフィスを持たない企業が増えている?「オフィスレス」な会社のメリットやおすすめのケース

近年、「オフィスを持たない」という働き方を選ぶ企業が増えています。リモートワークの普及やクラウドサービスの進化により、従来のような物理的なオフィスに縛られずに、業務を遂行できる環境が整ってきたことが背景にあります。
特にスタートアップや少人数のチームでは、固定費の削減や柔軟な働き方の実現を目的として「オフィスレス」を選択するケースが増加傾向です。しかし、すべての企業にとってオフィスが不要というわけではありません。
本記事では、オフィスを持たない働き方のメリットや注意点、そして導入に向いている業種や企業の特徴について解説します。今後の働き方の選択肢として、ぜひ参考にしてください。
オフィスを持たない選択肢が注目されている理由
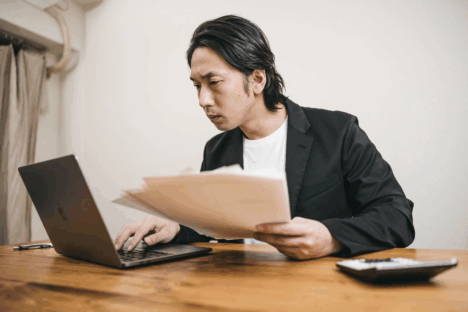
これまで、企業といえばオフィスを持つことが主流でした。しかし、近年はオフィスを持たない企業も珍しくなくなってきています。
なぜ今、オフィスを持たない選択肢が注目されているのか、以下から見ていきましょう。
オンラインでのコミュニケーションに抵抗を持つ人が減ってきている
オフィスを持たない選択肢が注目されている背景には、まずオンラインでのコミュニケーションへの抵抗感を抱く人が少なくなってきていることがあります。
2020年に流行した新型コロナウイルスの影響により、ビジネスシーンではオンラインでのやりとりが当たり前となりました。
現在でも、ビデオ通話を活用したMTGやリモートワークなど、新たなワークスタイルを継続している企業も多く、結果的にオンライン環境で対応できる人が増えています。
実際、新型コロナの影響で一気にリモートワークが普及し、多くの人がZoomやSlack、Chatworkなどのツールを扱える人は増加しました。つまり、以前は「対面でないと意思疎通が難しい」と感じていた人も、現在ではチャットやビデオ通話で十分に業務が進められる状況です。
上記の背景から、オンライン前提の働き方が社会に定着し、オフィスを持たない企業への抵抗感も薄れつつあるのです。
多様な人材獲得を目指したい企業が増えている
オフィスを持たないスタイルが注目されている理由の一つが、多様な人材を獲得したい企業にとって、適した選択肢であるからです。
働く場所に縛られない働き方を実現できれば、地方在住者や子育て中の人、高齢者や障がい者など、従来では採用が難しかった層も獲得しやすくなります。
実際、完全リモートを導入したIT企業の中には、地方に住む優秀なエンジニアや、子育てと両立できる主婦層を積極的に採用するケースも存在します。
働き方の選択肢を広げるだけで、企業は人材の多様性を高められるといっても過言ではありません。「オフィスを持たないこと」は、人材獲得の戦略としても期待できるでしょう。
起業のハードルを下げられる
「オフィスを持たない」といった考え方が注目されている理由として、起業ハードルが下がることが挙げられます。
オフィスを持たずに起業するということは、賃貸料や光熱費、家具代など、初期投資の負担を大幅に抑えることが可能です。
実際、クラウド会計やWeb会議ツールを活用すれば、パソコン一台で全国どこからでも事業をスタートできます。
「まずは小さく始めて、軌道に乗ってから拡大したい」と考える起業家にとって、オフィスを持たないスタイルは極めて合理的な選択肢なのです。
関連記事:働き方改革とは?制度の内容や現状の課題、具体例を簡単に解説!
オフィスを持たない企業のメリット

オフィスを持たないことで、どのようなメリットが得られるのかは気になるところでしょう。
ここからは、オフィスレスという選択肢の具体的なメリットを解説します。
人材不足の解消につながる
オフィスを持たない企業のメリットとして、まず挙げられるのが、人材不足の解決につながる可能性があることです。理由は、勤務地に制限がなくなるため、地理的な理由で就職できなかった層にもアプローチできるからです。
本記事でもすでに触れた通り、地方在住者や育児中の親、介護中の人など、時間や場所の制約がある人材も、リモートワークなら働きやすくなります。実際に、北海道在住の優秀なエンジニアが、東京の企業で在宅勤務で活躍する、といった事例は一般的です。
このように、オフィスを持たない仕組みを導入することで、都市部の企業でも全国規模で採用活動が可能になり、人材の選択肢が大きく広がります。
結果として、慢性的な人手不足に悩む企業にとっては、有力な解決策となるのです。
事業の拡大・縮小に柔軟に対応しやすい
オフィスを持たないといった選択肢は、事業規模の変動にも柔軟に対応しやすくなります。
物理的な拠点を持たない分、拡大や縮小の際に移転やレイアウト変更などのコストや手間がかかりません。仮に、新規プロジェクトで人員を10名増やしても、リモート環境であればデスクを追加したり、会議室を設けたりすることは不要です。
また、事業が縮小した場合も、不要となるオフィススペースの解約手続きや違約金などの負担が発生しません。一部のベンチャー企業の事例を見てみると、完全オフィスレスで、急成長に伴う人員増加にもスムーズに対応し、リスクなく事業を展開させています。
経営環境の変化に対応できるという点でも、オフィスを持たないスタイルは大きな武器になるでしょう。
サステナブルな事業展開ができる
オフィスを持たない企業は、環境負荷を抑えたサステナブルな経営スタイルを実現できるといったメリットがあります。オフィスレスを選ぶことで、通勤の削減によるCO2排出の抑制、オフィス設備にかかるエネルギー消費の減少などにつながるからです。
たとえば、従業員全員が在宅勤務する企業では、電車や車による通勤がゼロになり、環境への負荷を軽減できます。また、紙の書類を使わずにクラウド管理を徹底することで、ペーパーレス化も推進できるでしょう。
実際、サステナビリティに取り組む企業の中には、オフィスレスを戦略的に取り入れて、SDGsへの貢献や企業イメージの向上を図っているケースもあります。
オフィスを持たない働き方は、単なるコスト削減だけでなく、環境にやさしい経営の一環としても注目されているのです。
大幅なコスト削減ができる
オフィスを持たない最大のメリットのひとつは、固定費を大幅に削減できる点です。
家賃や水道光熱費、通信設備、清掃など、オフィスにかかるさまざまな経費がかかるものの、オフィスゼロにすれば大幅に抑えられます。
たとえば、都心のオフィスを月額50万円で借りていた企業が、オフィスレスに切り替えたことで年間600万円もの経費削減に成功した事例もあります。
浮いたコストは人材採用や研修、マーケティングなど、事業成長に直結する部分へ再投資することが可能です。
オフィスを持たないことで生まれる経済的なメリットは大きく、経営資源の有効活用にもつながるでしょう。
オンラインでのやりとりのほうが記録に残る
オフィスを持たないことは、必然的に離れたメンバーとオンラインでやりとりすることとなるため、やりとりの履歴を残しやすいのがメリットです。
チャットやメールなどのオンラインでの業務連絡は、やりとりの履歴が残るため、進捗管理に活用したり、認識のずれを防いだりできます。結果的に、業務効率を高めることが可能です。
実際、SlackやChatworkを活用している企業では、会話ログを見返したり、タスク設定を活用したりして、情報の整理・共有や、タスク管理を行っているケースがあります。
対面で仕事をする場合、口頭での指示が忘れられたり、メモの有無で内容に差が出ることもありますが、オンラインならいずれのミスも軽減しやすくなるでしょう。
業務の可視化やトラブル防止、後からの検証がしやすいという点でも、オンラインがメインとなる「オフィスレス環境」は魅力が大きいといえます。
関連記事:ハイブリッドワークとは?メリット・デメリットや導入のポイント
オフィスを持たない場合の選択肢

仮に「オフィスを持たない」といった選択肢を選ぶ場合、企業にはどのような道があるのでしょうか。
ここからは、オフィスを持たない場合の選択肢について解説します。
リモートワークの導入
オフィスを持たない働き方の代表例として挙げられるのが、リモートワークの導入です。
従業員が自宅やカフェなど、会社以外の場所で業務を行う働き方であり、インターネット環境があれば実現できます。
オンラインのツールを活用すれば、会議やチャット、資料の共有などもスムーズに進められるのが特徴です。環境を整えたうえで全従業員をリモートワークに移行することで、年間数百万円単位のコスト削減や、従業員満足度の向上を図ることも難しくありません。
実際、リモートワークの導入に伴い通勤が不要になったことで、ワークライフバランスが改善し、離職率が下がったといったケースもあります。
このように、リモートワークの導入は、コスト面だけでなく人材定着や生産性向上にも貢献する選択肢といえるでしょう。
バーチャルオフィスの導入
オフィスを持たずに法人として信頼性を維持する方法として、バーチャルオフィスの導入が挙げられます。
バーチャルオフィスとは、物理的なオフィスを設けるのではなく、住所や電話番号、郵便物の受け取りなどのサービスのみを提供するサービスのことです。
法人登記のために住所が必要な場合、バーチャルオフィスは便利な選択肢でしょう。仮に、都心の一等地にあるバーチャルオフィスを利用できたら、ブランドイメージを高めつつ、コストは月数千円~数万円程度に抑えられます。
つまり、バーチャルオフィスは、信頼性の高さだけではなく、実用性にも優れているといえるでしょう。
サテライトオフィスの活用
オフィスを持たない企業でも、業務効率やチームワークを重視して「サテライトオフィス」を活用するケースがあります。サテライトオフィスとは、本社以外の場所に設置された小規模な勤務拠点のことで、自宅から通いやすい場所に設置される傾向です。
サテライトオフィスは、完全在宅での業務に不安のある社員や、チーム単位でのコミュニケーションが必要な業務に最適です。
たとえば、大手通信会社の一部では、郊外にサテライトオフィスを設置し、子育て中の社員が自宅近くで働けるように環境を整備しています。
サテライトオフィスは従業員の通勤負担を軽減しつつ、集中できる環境を確保できるため、働きやすさと業務効率を両立できるのが魅力です。
ちなみに、富士宮市では地方に拠点を設けたい企業や、地方の人材に配慮したい企業などに向けたサテライトオフィス誘致事業を展開しています。
資源の豊富な富士宮市は、ビジネスの街としても認知されつつあり、大手企業から中小企業に至るまでさまざまな企業に注目されてきています。
オフィスを持たないといった選択肢を検討している方は、ぜひ富士宮市のサテライトオフィス事業も視野に入れてみてください。
【富士宮サテライトオフィス】
窓口 :富士宮市 産業振興部 商工振興課
電話番号:0544-22-1154
公式HP :https://fujinomiya-so.com/
コワーキングスペースの活用
コワーキングスペースの活用は、オフィスを持たない企業にとっての選択肢の一つです。コワーキングスペースは、さまざまな企業や個人などが共同で使用するワークスペースです。設備環境が充実しているスペースが多く、インターネット環境や会議室、プリンター、テレフォンブースなどが完備されている傾向にあります。
月額での契約は必須ではなく、必要なときにだけ利用(ドロップイン利用等)が可能なため、固定費を抑えながら業務環境を整備できます。
仮に、完全リモートワークを導入している企業であれば、定例ミーティングや社員研修の際にコワーキングスペースを時間単位で借りるといった活用方法も可能です。
また、他の異業種の利用者との交流を通じて、ビジネスチャンスや刺激を得られるのも魅力でしょう。普段交流することのない業界と繋がることができれば、事業に良い影響を与えられる可能性もあります。
コワーキングスペースは、単純な「業務スペース」として利用するだけではなく、交流やビジネスチャンスも期待できる有益な場所なのです。
なお、富士宮市には、オフィスを持たない企業・事業主に最適なコワーキングスペース「Connected Studio i/HUB」があります。インターネット環境やプリンター、会議室など、業務に必要な設備は一通り揃っているため、事前の準備不要ですぐに活用することが可能です。
さらに、個室ブースや図書コーナーなど、集中して業務に取り組んだり、自己研鑽に励める環境も整っています。さまざまな活用スタイルがあるのは、Connected Studio i/HUBのメリットでしょう。
イベントが豊富であるうえに、マッチングサービスも充実しているため、異業種の利用者との交流や、情報収集も可能なスペースであるため、成長も視野に入れたい方は、ぜひ利用を検討してみてください。

【Connected Studio i/HUB】
住所 :静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル1F/2F
営業時間:9:00~18:00(月額会員は24時間利用可能)
休業日 :土曜日・日曜日・祝日・その他
電話番号:0544-66-6880
公式HP :https://connectedstudioihub.com/access/
関連記事:サテライトオフィスとレンタルオフィスとの違いは?様々な形態のオフィスとの違いを解説
オフィスレスがおすすめのケース

オフィスレスの働き方は、魅力的なメリットが豊富ですが、必ずしもすべての企業に適しているわけではありません。そのため、そもそもどのような企業にオフィスレスがおすすめなのかを把握しておく必要があります。
ここからは、オフィスレスがおすすめのケースについて、詳しく解説していきます。
PC・インターネットがあれば完結する業種・業態
オフィスレスなスタイルが最もおすすめなのは、PCとインターネットさえあれば仕事が完結する業種や業態です。IT企業やWeb制作関連の企業のほか、ライターやデザイナー、マーケティングなど、デジタル上で完結する業務を行っている場合、オフィスを持たずに業務を進めやすい傾向があります。
まずは、自社の業務内容を整理し、「外出の頻度」「外部との打ち合わせ・MTGのスタイル」「PC以外に必要な設備の規模」などをふまえ、オフィスレスが現実的であるかを考えてみましょう。
スタートアップ企業・起業間もない事業主
オフィスレスがおすすめできるケースの一つが、スタートアップ企業や、起業して間もない事業主などです。オフィスを持たないという選択肢は、固定費の削減と柔軟な働き方の両立を実現できます。
社員数が少なく意思決定が早いスタートアップ企業であれば、オフィスレスの柔軟性は相性が良い傾向です。また、資金に限りがある「起業したばかりの個人事業主」にとって、コストを抑えやすいオフィスレスは無理のない選択肢として選びやすいでしょう。
これから起業を検討している方や、個人事業主として独立したい方などは、オフィスレスが適している可能性が高いと考えられます。
従業員のライフスタイルが多様な企業
所属している従業員のライフスタイルが多様であれば、オフィスを持たない選択肢はおすすめです。現代は、育児や介護、二拠点生活の実現、心身に障がいがあるなど、さまざまなライフスタイルを持つ人が増えています。
従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態は、現代においてニーズが高いスタイルです。オフィスレスは、そんな多様なライフスタイルに対応するための働き方として注目されています。
「従業員が都合の良い場所で働ける」「通勤が困難な従業員も無理のない範囲で活躍できる」「ワークライフバランスを重視した働き方ができる」といった企業は、多様なライフスタイルを実現しているといえるでしょう。
オフィスを持ったほうがよいケース

オフィスを持たないことが適しているケースがある一方、オフィスを持ったほうが良い場合も多いです。
ここからは、オフィスレスよりも、オフィスを設けたほうがよいケースを詳しく解説します。
対面でのコミュニケーションが多い場合
業務の中で対面コミュニケーションが重視される場合、オフィスを持ったほうが良い場合が多いです。直接会って話すことで得られる信頼関係は、オンラインで同じように構築することが難しい傾向にあるからです。
たとえば、広告代理店やコンサルティング会社であれば、社内外の打ち合わせやプレゼンなどの場で、参加者の表情や空気感を読み取りながら進める力が成果に関わります。
また、アイデアを出し合うブレインストーミングや雑談から生まれるひらめきなど、対面のほうが有利な場合も少なくありません。
対面でのコミュニケーションが多い業務スタイルの場合、オンラインだけではコミュニケーションの質も下がる恐れがあるため、オフィスを設けて人間関係や信頼関係の構築、成果の向上につなげることが重要です。
現場対応が求められる業種
製造業や建設業、医療、小売飲食など、業務の一環として、現場対応が求められる業種は、オフィスを設けたほうが良い場合が多い傾向にあります。
現場対応が多い業種の場合、リモートでは完結できない業務が多いため、人が集まれる場所が必要です。
製造業であれば、工場や設備を管理するための現場対応が必要ですし、小売や飲食では実際に接客・提供を行う場所がなければ業務が成り立ちません。医療現場においても、チーム医療や緊急対応など、リアルタイムの連携が求められる場面も多いため、対面の業務体制が必須です。
いずれも、オフィスという特定の拠点が運営の土台となっているため、リモートで対応できる範囲は限られています。そのため、現場主導型の業務には、オフィスの存在が必須と考えられるのです。
若手社員や新卒社員が多い企業
若手社員や新卒社員が多い企業では、オフィスでの直接指導やチームとの対面交流が非常に重要です。なぜなら、社会人としての基本的なマナーや業務の進め方を、実際の現場で体感しながら学ぶ必要があるためです。
新卒1年目の社員が完全リモート勤務になった場合、仕事の相談がしにくく、孤独を感じたり不安を覚えたりしやすくなる傾向があります。「仲間と一緒に働いている」といった感覚も得にくいため、帰属意識が芽生えにくくなることも懸念点です。
また、先輩社員からの声かけや、指摘などをこまめに受けられないと、成長のスピードにも影響してしまいます。その場ですぐに注意や指摘、アドバイスがあればすぐに自分のやり方に反映しやすくなるものの、リモートワークではリアルタイムでのスピーディーなフィードバックは難しいものです。そのため、若手社員や新卒社員などが多い企業は、オフィスレスが向かない可能性があります。
一部の企業では「週数回は出社日を設けてOJTの機会をつくる」といったハイブリッド型の工夫もされているものの、育成が中心の企業では、やはり対面で集まれる環境が重要です。
まとめ
オフィスを持たない「オフィスレス」な働き方は、これからの時代においてメリットの大きい選択肢の一つです。特に、IT業やクリエイティブ職、スタートアップなどでは、オフィスレスの導入によって業務効率や社員満足度が向上したという事例も増えています。
とはいえ、業務内容や組織文化によっては、リアルな対面環境が必要なケースがあることも忘れてはいけません。オフィスの有無を検討する際には「どちらが優れているか」ではなく、「自社にとって最適かどうか」で判断しましょう。
また、サテライトオフィスやコワーキングスペースなどの活用を検討している方は、ぜひ富士宮市をご検討ください。
ビジネスに必要な環境が充実している、資源豊かな街で、ぜひ新たなチャレンジをスタートさせてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・お申込みはこちら
よく読まれている記事

