SCROLL DOWN
INFORMATION
リモートワークとは何かを簡単に解説!テレワークとの違いや導入メリット、成功ポイントを解説

近年、「リモートワーク」という働き方が広く普及し、多くの企業や個人が導入を進めています。 インターネット環境とITツールの進化により、自宅やカフェなどオフィス以外の場所でも働けるようになり、働き方の多様化が加速しています。
ただ、「テレワーク」との違いや、実際に導入するメリット・デメリットが分かりづらいと感じている方も少なくありません。
そこで、本記事では、リモートワークとは何かを初心者にも分かりやすく解説し、テレワークとの違いや導入のメリット、成功のポイントまで詳しく解説します。
リモートワークとは?概要を簡単に解説
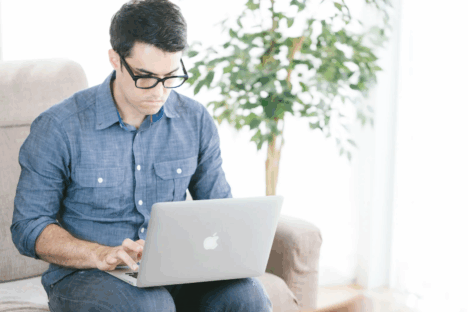
リモートワークとは、会社のオフィスに出勤せずに、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、離れた場所で働くスタイルのことです。「remote(離れた)」という英単語の通り、物理的に職場から離れていても業務をこなす働き方です。
インターネットやクラウドサービスの発展により、パソコン1台とネット環境があれば、資料の共有から打ち合わせ、報告などがスムーズにできるようになりました。代表的なツールとしては、ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議、SlackやChatworkなどのチャットツール、GoogleドライブやDropboxといったクラウドストレージが活用されています。
リモートワークの魅力は、通勤時間を削減し、働く場所や時間の自由度を高められることです。現在では、IT業界を中心に多くの企業がリモートワークを導入しており、働き方改革や人材確保の観点からも注目されています。
つまり、リモートワークとは「オフィスにいなくても、成果を出せる働き方」とも言えるでしょう。
関連記事:ホテリングとは?注目される理由やメリット・デメリット、導入方法を解説
リモートワークとテレワークとの違い
「リモートワーク」と「テレワーク」は似た言葉ですが、実は意味に少し違いがあります。
結論から言うと、「リモートワークはテレワークの一種」です。
テレワークとは、「tele=離れた場所」と「work=働く」を組み合わせた言葉で、オフィス以外の場所で仕事をするすべての働き方を含む広い概念です。
一方、リモートワークは、テレワークの中でも、特に「自宅や遠隔地でパソコンやインターネットを使って働く形態」にフォーカスした用語として使われることが多いです。
たとえば、テレワークには「在宅勤務」「モバイルワーク(外出先での業務)」「サテライトオフィス勤務」なども含まれますが、リモートワークは主に在宅勤務を意味する場合が多くなっています。
つまり、テレワークは政府や自治体などの公的な文書でも使われる「包括的な言葉」、リモートワークは企業やメディアでカジュアルに使われる「具体的な働き方」といえます。
ただ、企業や現場によっては、リモートワークやテレワークを明確に定義していない場合もあるため注意しましょう。
リモートワークを導入するメリット
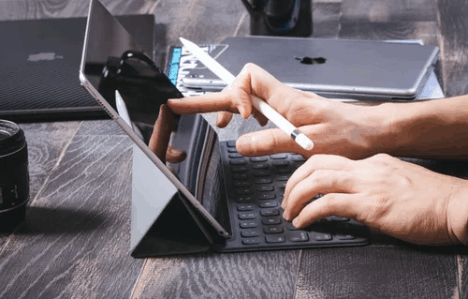
リモートワークを導入することで、企業・従業員の双方にメリットがあります。ここからは、企業におけるリモートワークの導入メリットを見ていきましょう。
生産性を向上できる
リモートワークを導入するメリットの一つとして、まず挙げられるのが業務の生産性を高められることです。通勤時間の削減や、個人に合った環境での仕事が可能になるため、従業員が空いた時間を自己研鑽に活用したり、集中力を維持したりしやすいといえます。
実際、毎日の通勤に往復2時間かかっていた社員が、その時間を業務や学習に充てられるようになったことで、成果が向上したという事例もあるのです。また、社内の雑談や不要な会議が減り、タスクを中心として動くことが習慣化されるため、効率的に仕事を進める意識が高まります。
もちろん、リモートワークには集中できる環境の整備や、怠慢にならないような自己管理力が必要ですが、業務の進め方を整備すれば、オフィス勤務以上のパフォーマンスを発揮する社員も少なくありません。
時間の使い方の自由度を高められる、リモートワークは企業の生産性向上に貢献するでしょう。
コストを削減できる
リモートワークの導入で期待できるメリットが、コスト削減効果です。企業は、リモートワークを導入することで、固定費や変動費を削減できます。オフィスの賃料や光熱費、通勤交通費、備品代など、物理的な空間にかかるコストが大幅に減るからです。
仮に、オフィスを構えている企業が、完全リモートへ移行した場合、年間1,000万円以上の経費を削減できる可能性もあります。浮いた分のコストは人材育成や広告費に再投資するといった選択肢も生まれ、より事業の成長につなげることが可能です。
また、従業員が自宅で働くことで通勤手当の支給も不要になり、福利厚生費も抑えられます。従業員が多い企業であるほど、メリットの大きい選択肢なのではないでしょうか。
ペーパーレス化や業務のデジタル化においても、印刷代や郵送費といった見えにくいコストの削減が期待できます。リモートワークは単純に働き方を変えるだけではなく、企業全体の経営効率を改善すると言えるのです。
BCPの体制を構築できる
リモートワークの導入は、BCP(事業継続計画)の体制をつくることにつながります。災害やパンデミックなど、有事の際にも業務を止めずに継続できる体制は、日本において必須です。
たとえば、2020年の新型コロナウイルス流行時には、オフィスでの勤務が前提であった企業は業務停止を余儀なくされました。しかし、リモートワークをすでに導入していた企業は、スムーズに業務を継続できたといった事例があります。
また、リモートワークを導入することで台風や地震、インフルエンザの流行といった日常的なリスクにも強くなるでしょう。結果的に、従業員の安全を守りながら、事業を止めることなく稼働できる環境を得られます。
非常時に対応しやすい体制を構築できる点は、リモートワークの大きなメリットでしょう。
関連記事:オフィス改革とは?目的や効果、導入したいアイデアまとめ
リモートワークを導入する際の注意点

リモートワークの導入には、さまざまなメリットがある一方で、いくつか注意すべきポイントも多いです。
ここからは、リモートワークを導入する前に把握しておくべき注意点を解説します。
コミュニケーション不足に陥りやすい
リモートワークの導入において最も多い課題の一つが、コミュニケーション不足です。オフィスでのような雑談や気軽な声かけがなくなり、社員同士のつながりや情報共有が希薄になりやすいといった難点があります。
コミュニケーション不足は、チームの一体感が損なわれたり、ミスや認識のズレが発生したりするリスクが高まるため、避けなければならない問題です。
たとえば、業務上の報告がチャットだけで済まされ、細かいニュアンスが伝わらず、クライアント対応でトラブルになるリスクがあるでしょう。場合によっては、クレームや契約解消など、深刻なトラブルに陥るかもしれません。
コミュニケーション不足を防ぐには、定例ミーティングを実施したり、カジュアルに話せるオンライン雑談の時間を設けたりするなど、意識的にコミュニケーションの機会を増やすことが重要です。
リモート環境では「自然な会話」が起きにくいため、仕組みとしてコミュニケーションの時間を設けることが、信頼関係や仲間意識を維持するためにも必要でしょう。
業務を見える化することが難しい
リモートワークにおいて、難点となるのが「業務を見える化しにくい」です。お互いに同じ空間で業務をしているわけではないため、誰が何をしているかが見えにくくなるという課題があります。
オフィスなら目の前にいたり、雑談の中で進捗が伝わることが多いものの、在宅勤務ではオフラインのように自然に進捗を把握することはできません。
業務が見えないと、上司は適切な指示や評価ができず、メンバー間でも連携ミスが起きやすくなります。場合によっては、すでに完了したタスクを、別の従業員が作業を重複して行ってしまった…といった無駄が発生するかもしれません。
これを防ぐには、タスク管理ツール(TrelloやBacklog、Notionなど)を活用し、プロジェクトごとの進捗や担当を「見える化」する必要があります。あわせて、定期的な進捗報告や、KPIの共有といったルールを設けることも重要でしょう。
「誰が何をしているのか」と、業務を見える化することが、リモートワークでは必須といえます。
オンラインツールの活用が求められる
リモートワークでは、オンラインツールの活用スキルが必須です。対面のやりとりができない分、連絡や会議、資料共有などは、ほぼすべてオンラインで行う必要があるからです。
そのため、社員全員がオンラインツールに慣れていないと、かえって業務効率が落ちたり、情報伝達に支障が出る可能性があります。
もし、Zoomの使い方がわからない社員がいた場合、会議に参加できず、参加や進行に支障をきたしてしまう恐れがあります。
導入する際には、使用するツールの導入を促すだけでなく、基本的な操作方法を研修やマニュアルで周知することが重要です。
リモートワークを成功させるためのポイント

リモートワークを導入しても、必ずしも成功させられるとは限りません。正しいポイントをおさえたうえで導入する必要があります。
ここからは、リモートワークを成功させるためのポイントを解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
ITツールを使いこなせるように体制を整える
リモートワークを成功させるうえで最も重要なのが、ITツールを使いこなせる体制の整備です。リモートワークを導入すると、出社しない限り、ほとんどの業務をオンラインで行うこととなります。
そのうえ、一口に「ITツール」といっても、チャットツールやWeb会議ツール、ドキュメント共有、タスク管理など、用途に応じて複数のツールが存在します。そのため、それぞれを使いこなす必要もあるのです。
しかし、ツールを使用できるレベルに従業員間で差があると、うまく業務が進まなくなってしまいます。そのため、導入時にはツールにおけるルールづくりや社内研修での使用方法のレクチャーなどが必要です。
誰でも使える環境を整え、操作に迷わないようにすることで、業務効率やコミュニケーションの質、セキュリティのすべてを向上できます。
リモートワークは、IT環境がインフラとなるため、まずはツール回りを整えることが重要です。
成果重視の評価に切り替える
リモートワークを成功させるためには、評価基準を「時間」ではなく、「成果」へ切り替えることが重要です。リモートワークでは、オフィスのように勤務態度や労働時間を目で見て判断することができません。そのため、「どれだけ働いているか」ではなく「何を成し遂げたか」が評価軸になるからです。
たとえば、出勤して8時間座っていた社員より、短時間で高い成果を上げた社員の方が会社に貢献しているケースがあります。リモート環境では、自律的に働ける人材ほど力を発揮するため、KPIや納期、タスクの完了度などの具体的な成果にもとづいた評価制度を整えましょう。
一例としては、週単位で成果を共有する仕組みを導入し、上司もメンバーも成果を客観的に振り返る文化を育てていくことが挙げられます。常に、成果が見える化されていれば、従業員全体が向上心を持って業務に取り組みやすくなるでしょう。
従業員全体の成果が向上できれば、企業の成長にも影響するため、評価方法はリモートワークに適した方法を採用することが重要です。
関連記事:オフィス分散とは?メリットや導入方法、注意点について解説
リモートワークの成功しやすい導入方法

リモートワークを導入するにあたり、どのような方法を取り入れれば成功しやすいのかは気になるポイントです。
ここからは、リモートワークの成功しやすい導入方法を解説します。
サテライトオフィスを活用する
リモートワークの導入を成功させるためにも、まず知っておきたいのがサテライトオフィスです。本社とは別に、小規模な拠点を地方や郊外に設け、社員が自宅以外で働ける場所を確保する方法です。
在宅ワークに必要な設備が不十分な従業員や、自宅では集中できないといったケースなどで導入を検討されることが多い傾向にあります。また、「自宅から本社までの通勤時間が長い」といった問題を抱えている従業員のために、自宅近くにオフィス環境を確保することを目的として、サテライトオフィスが選ばれることも多いです。
郊外に複数のサテライトオフィスを設置することで、社員の通勤時間を平均で1時間以上短縮できる場合もあり、結果的に生産性向上や、従業員の満足度アップを実現できる可能性があるのです。
リモートワークは必ずしも在宅ワークである必要はないため、サテライトオフィスの導入はおすすめです。在宅ワークとオフィス勤務の中間的な立ち位置であるサテライトオフィスは、リモートワークを成功させるためにも有効といえます。
ちなみに、富士宮市では、中小企業や大手企業向けにサテライトオフィス事業を展開しています。ニーズにマッチするサテライトオフィスの案内や、富士宮市でのビジネス展開に関する窓口を設置しているため、さまざまなビジネスチャンスを得られます。
「本社以外に拠点が欲しい」「在宅以外の業務環境を確保したい」と考えている方は、ぜひ富士宮市のサテライトオフィスを検討してみてください。
【富士宮サテライトオフィス】
窓口 :富士宮市 産業振興部 商工振興課
電話番号:0544-22-1154
公式HP :https://fujinomiya-so.com/
ハイブリッドワークを取り入れる
リモートワークを成功させるための選択肢の一つが、ハイブリッドワークを取り入れることです。
ハイブリッドワークとは、オフィス勤務とリモート勤務を組み合わせる働き方を指します。完全通勤や完全リモートと比べて自由度が高く、企業側と従業員側のメリットがあるのが特徴です。
全員が毎日出社する必要はない一方で、定期的に対面で集まる機会を設けられるため、チームの連携がスムーズになったり、会社の文化を維持しやすくなったりします。
通勤と在宅の頻度は企業によって異なるものの、「週2日出社・週3日リモート」のようにルールが明確であるケースが多い傾向です。
リモートワークのメリットを活かしつつ、チームの一体感や創造性も高められるハイブリッドワークは、特に中規模以上の組織にとっておすすめのスタイルです。
コワーキングスペースを利用する
リモートワークを成功させるための方法として、「コワーキングスペース」を活用する方法があります。コワーキングスペースは、複数の企業や個人が共有して利用するワークスペースのことです。
インターネット環境や作業デスクなどはもちろんのこと、会議室、プリンター、カフェなどの設備が整っているコワーキングスペースもあります。自宅では作業に集中できない、もしくは働く環境を定期的に変えたい、といった社員にとっては、理想的な働く場所となります。
また、コワーキングスペースは全国にあるうえに、都度利用が可能でもあるため、地方出張の際の作業場所として気軽に利用できたり、次の予定までの待ち時間を有効活用したりできます。
月額での契約も可能であるため、サテライトオフィス感覚で「従業員のための特定の拠点」として活用することも可能です。
富士宮市は、サテライトオフィスのほか、コワーキングスペースも充実しています。「Connected Studio i/HUB」は、富士宮市で運営されているコワーキングスペースであり、起業家やフリーランス、会社員など、利用者は多岐にわたります。
都度利用のドロップインや、月額契約など、利用スタイルも多岐にわたるため、目的に応じて導入できるのが魅力です。
コワーキングスペースの活用を検討している方は、ぜひ一度「Connected Studio i/HUB」の利用も視野に入れてはいかがでしょうか。

【Connected Studio i/HUB】
住所 :静岡県富士宮市大宮町31 澤田ビル1F/2F
営業時間:9:00~18:00(月額会員は24時間利用可能)
休業日 :土曜日・日曜日・祝日・その他
電話番号:0544-66-6880
公式HP :https://connectedstudioihub.com/access/
オンラインスペースで共同作業する
リモートワークを成功させるための方法の一つが、オンラインスペースでの共同作業です。各従業員がバラバラの場所で働く中でも「一緒に働いている感覚」を持つことは大切です。
一緒に働いているような感覚を得るための方法としておすすめなのが、オンラインスペース(仮想の作業部屋)での共同作業です。
たとえば、「oVice」「Remo」「oasis」などのツールを使えば、仮想空間でメンバーがアバターやアイコンで常駐でき、気軽にコミュニケーションを交わしながら作業ができます。
また、仮想のオンラインスペースは、リアルでのコミュニケーションと似た距離感が再現されているため、適度な緊張感も得られるのが魅力です。
オンラインスペースを活用すれば、完全リモートでも「チームの一体感」を得られるでしょう。業務効率だけでなく、心理的な距離も縮められるツールであるため、物理的な空間ではなく、オンライン上で似た環境を整備したいといった企業におすすめです。
まとめ
今回はリモートワークとは何かを解説しました。リモートワークは会社以外の場所で働く自由なワーキングスタイルのことです。
ただ、必ずしも成功するとは限らないスタイルであるため、「どこで働くか」以上に「どう仕組みを整えるか」が重要です。
従業員のために、働き方改革や、ワークスタイルの改善を検討するのであれば、ぜひリモートワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・お申込みはこちら
最近よく読まれている記事

